『沈黙』:遠藤周作
始めて『沈黙』を読んだのは20代後半だったと思う。読み終えたとき、もう読み返したくないと思った。怖かった。自分だったらどうする、と主観的に読んだからでしょう。神と信仰を命題にした重い小説です。
映画が公開されているので読み返して見た。始めて読んだときの怖さは感じない。若いとき直面していたストレス、それに緊張感を失ったからでしょうか。
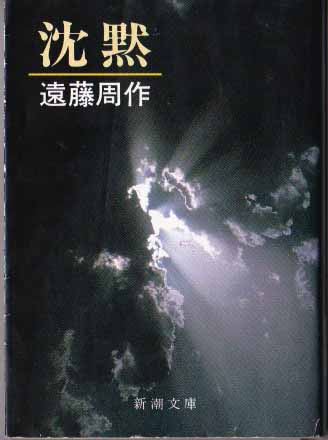
物語は、1938年3月に若い司教たちが日本に密入国するためにポルトガルを出港したところから始まる。1937年、日本は島原の乱で一揆を起こした農民、切支丹が37,000人が幕府軍によって一人の残らず虐殺され、切支丹禁令が一番厳しい時代だった。
日本へ密入国する目的は、ポルトガルのイエズス会の最高の重職にあり、日本で二十年布教活動していた司教フェイリスが「長崎で穴吊りの拷問をうけ、棄教を誓った」という消息を知るため、そして司祭を失って孤立している信徒を勇気づけ、フランシス・ザビエル以来の信仰の火種をたやさないためだった。
主人公の司教ロドルコと司教バリアは、マカオで会った狡そうな目をした日本人、キチジローの案内で、小さな密航船で長崎の海岸にたどり着く。このキチジローも切支丹だった。キリストを裏切ったユダのような人間で、彼らの運命に関わることになる。
物語の結末は容易に想像できる。二人の司教が捕らえられて処刑されるか、拷問死するか、拷問に屈し「転ぶ」(棄教)かである。青い空も、海もない、薄汚れたモノクロームのなかを一直線に結末に向かっていく。そこには神の光も、幸運も、どんでん返しもない。
2人の司教を匿った部落の2人が海に張り付けられ拷問死した。
殉教でした。しかし何という殉教でしょう。私は長い間、聖人伝に書かれているような殉教をーたたえばその人たちの魂が天に帰る時、空には栄光の光がみち、天使が喇叭をを吹くようなかがやかしい殉教を夢みすぎました。—-日本信徒の殉教はそのようなかがやかしいものでなく、こんなにみじめで、こんなにつらいものだったのです。ああ、雨は小やみになく海にふりつづく。そして、海は彼らを殺したあと、ただ不気味に押し黙っている。——-
何を言いたいのでしょう。自分でもよくわかりませぬ。ただ私にはモキチやイチゾウが主の栄光のために嘆き、苦しみ、死んだ今日も、海が暗く、単調な音をたてて浜辺を噛んでいることが耐えられぬのです。この海の不気味な静かさのうしろに私は神の沈黙を—神が人々の嘆きの声に腕をこまぬいたまま、黙っていられるような気がして…..
キチジローが司教ロドリコに、
「俺には俺の言い分があっと、踏み絵ば踏んだ者には、踏んだ者の言い分があっと。—俺が喜んで踏んだとも思っとっとか。—–俺を弱き者に生まれさせながら、強か者の真似ばせろとデウスさまは仰せ出される。それは無理無法と言うもんじゃい」
そして捕らえられた。ここからが物語の核心です。井上築後守は、もの静かに、冷酷な方法で、ロドリコを追い込んでいく。穴吊りされた信徒の呻き声。彼らを救うためにロドルコは踏み絵を踏んで「転んだ」(棄教)のか? キリストの声が聞こえる。
では物語のなかで、私は誰と置き換えられるだろうか、考えるまでもないキチジローです。弱い人間です。
Amazon➡️沈黙 (新潮文庫)
楽天➡️沈黙改版 [ 遠藤周作 ]