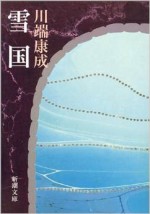川端康成の「雪国」
川端康成の「雪国」で知っていたことは「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」だけでした。
2007年の12月、新潟の出張の帰りに新幹線で「雪国」を初めて読みました。土地柄本屋に「雪国」が山積みされていました。
新幹線のなかで読み始めて作家はすごいなと思いました。小説冒頭の列車の中、列車の窓に映る反対側の座席に座っていた女性の横顔と窓を通して見える夕景色の二重写しの描写です。
写真、動画よりもイメージが記憶に残る、情景、叙情表現です。この「雪国」が、あらためて文学小説を読み始めたきっかけでした。
その部分の一部引用です。
—-鏡の底には夕景色が流れていて、つまり写るものと写す鏡とが、映画の二重写しのように動くのだった。登場人物と背景とはなんのかかわりもないのだった。しかも人物は透明のはかなさで、風景はタ闇のおぼろな流れで、その二つが融け合いながらこ世ならぬ象徴の世界を描いていた。殊に娘の顔のただなかに野山のともし火がともった時には、島村はなんともいえぬ美しさに胸が震えたほどだった。—-
—-汽車のなかもさほど明るくないし、ほんとうの鏡のように強くはなかった。反射がなかった。だから、島村は見入っているうちに、鏡のあることをだんだん忘れてしまって、夕景色の流れのなかに娘が浮んでいるように思われて来た。
そういう時、彼女の顔のなかにともし火がともったのだった。この鏡の映像は窓の外のともし火を消す強さはなかった。ともし火も映像を消しはしなかった。そうしてともし火は彼女の顔のなかを流れて通るのだった。しかし彼女の顔を光り輝かせるようなことはしなかった。冷たく遠い光であった。小さい瞳のまわりをぼうっと明るくしながら、つまり娘の眼と火とが重なった瞬間、彼女の眼はタ閣の波間に浮ぶ、妖しく美しい夜光虫であった。—